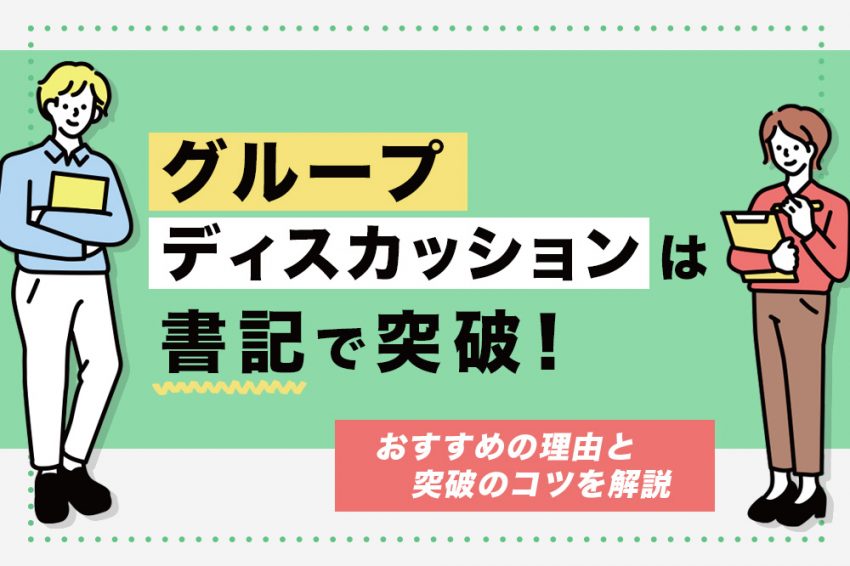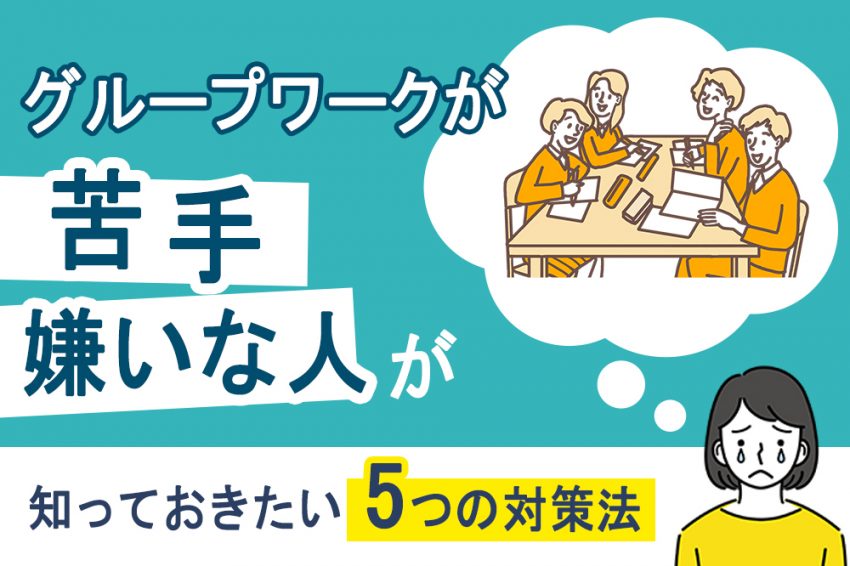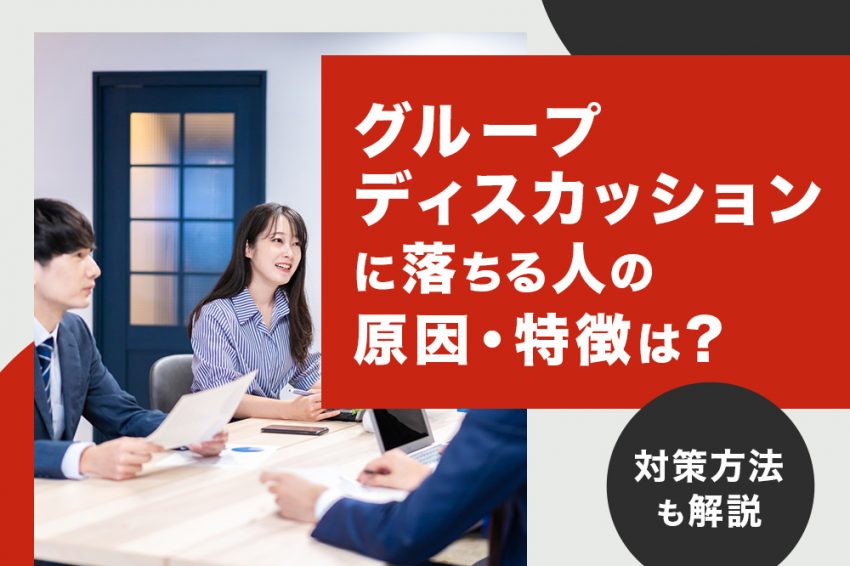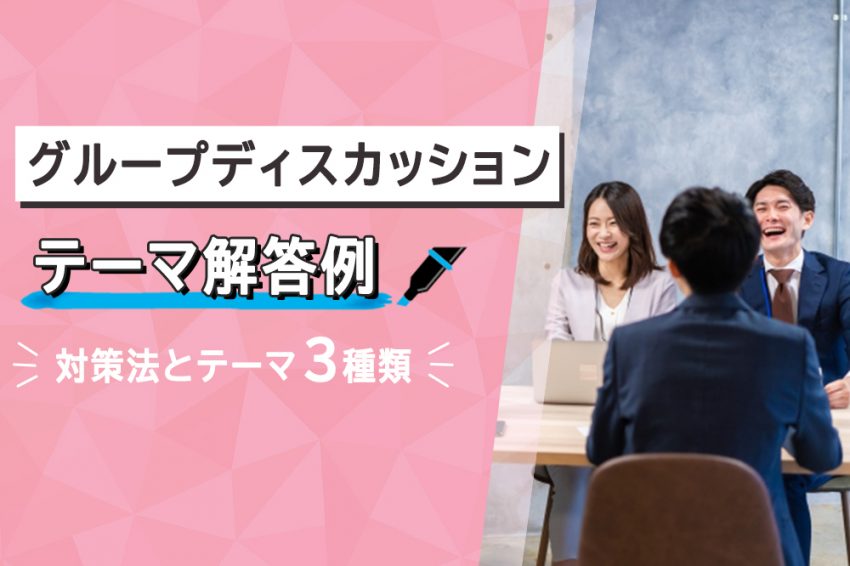- 「グループディスカッションを突破できない……」
- 「グループディスカッションにコツなんてあるの?」
このように悩んでいませんか?
実は、グループディスカッションは書記を担当して議論をまとめることで選考突破に近づくんです!
この記事では、グループディスカッションの基本的な流れと選考突破のための振る舞い、やりづらい人とグループになった時の対処法を解説します。
本記事を読めば、グループディスカッションでの振る舞い方のコツを知ることができ、どんな人とグループになっても上手にディスカッションを進められるようになりますよ!
そもそもグループディスカッションが、どんな選考かを知りたい方はこちらも参考にしてみてください。グループディスカッションの流れや必要な力について解説しています。

| 選考対策に強い就活サイト | ||
|---|---|---|
| エージェント名 | 評価 | ポイント |
>> OfferBox公式へ | ★5.0 | 【自分の強みがわからない方へ】 28項目の診断で自分の適性を知ることができる |
>> キャリアチケット就職スカウト公式へ | ★4.8 | 【選考対策が苦手な方へ】 5つの質問から自己PRやガクチカの作成も簡単に作成できる |
>> Lognavi公式へ | ★4.5 | 【性格テストで自分にあった企業を見つけられる】 5段階の相性診断で自己理解が深まる |
グループディスカッションは集団での振る舞いを見る選考

グループディスカッションとは、学生数人のグループで、あるテーマに対する結論を話し合いで出し、発表するという流れの中で学生の集団での振る舞いを見る選考です。
グループディスカッションが導入されている目的として、面接では分からないチームでの動き方を知るということが挙げられます。
実際の業務はほとんどチームで行うため、企業はチームの中で活躍できる、もしくはチームの価値を引き出すことができる人材を求めています。
そのため、グループディスカッションを行うことで、学生がチームの和を乱さないか、協力して物事を進められるか、チームメンバーの価値を引き出すことができるかなどを確認でき、自社で活躍してくれる人材かを見極めることができるのです。
グループディスカッションについての概要が知りたい方は、以下の記事を参考にしてみてください。
グループディスカッションとは何かといった基本的なことから、見られている能力などについて紹介しています。

グループディスカッションはどのように進む?

グループディスカッションを突破するには、まず選考の流れを把握することが大切です。
グループディスカッションは、主に以下のような流れで進みます。
1.役職決め
企業の方からテーマが発表され、グループディスカッションが始まったら、まず役職決めをします。
司会や書記、タイムキーパーなど、自分の適性や今何をすべきかを考慮して役割を決めます。
ただし、先ほども述べたように、役職は必ずしも最初に決定する必要はありません。
むしろ、議論が進む中で自然に決めていったほうがその時に本当に必要なことを適切に実行できる可能性が高まります。
2.資料の読み込み
次に、具体的な案を出すための前提条件となる情報を得るために、資料の読み込みを行います。
市場の動向はどのようであるか、現在どのようなことが課題となっているかなどの情報を資料から読み取ります。
3.定義付け
与えられたテーマに対して定義付けをします。テーマは抽象的である場合が多いため、テーマを具体的に定義して施策に落とし込みやすくします。
たとえば、「若年層の売り上げを2倍にする施策を考えよ」というテーマが与えられた場合、若者とは何歳付近の人を指すのか、性別はどちらにするのかなどを定義することで、議論が噛み合わなくなることを防ぎます。
また、「売上を2倍にする施策」というのは、購入者を2倍にする施策なのか、一人当たりの売上を2倍にする施策なのかという観点でも絞り込むことが必要です。
4.アイデア出し
定義が定まったら、資料がある場合はその分析に基づいて施策の案を出します。
ここでは極端にアイデアを絞ることをせず、ある程度現実的で妥当性があれば採用していいでしょう。
この段階では粗探しに終始するのではなく、それぞれの良い面に目を向けてみるようにしましょう。
5.アイデアの検討とまとめ
アイデアが出たら、複数のアイデアの中から採用するものを選び、ホワイトボードや紙にまとめます。
ここではそれぞれのアイデアのメリットとデメリットを把握し、採用するアイデアに採用しないアイデアの良い面を取り込むなど、多角的な視野を持つことが重要です。
そして施策が決定したらホワイトボードや紙にまとめていきます。
時間があれば、施策を実行する際の課題点を洗い出し、質疑応答に備えられるとより良いでしょう。
6.発表・質疑応答
最後に人事に向けてグループディスカッションの成果を発表し、質疑応答を行います。
発表者を決めてプレゼンをする場合と、全員が発表する場合があり、発表者を決める場合はグループワークの時間内に決めておく必要があります。
発表をする際は、必要事項を簡潔に述べて冗長にならないようにしましょう。
グループディスカッションでの役職4つ

グループディスカッションでは、多くの場合それぞれの学生に役割が割り当てられます。
ここでは、グループディスカッションにおける主な役割を紹介します。
1.司会
司会は、議論を深めたり円滑に進めるためのまとめ役としての役割を果たします。
具体的には、議論が煮詰まったときに今までの話を整理したり、あまり発言の機会がない人に対して「どう思いますか?」などと話を振る行動が求められます。
2.書記
書記は、議論していることを分かりやすく書き記す役割を果たします。
グループメンバーが話した内容を忘れずに記録すること、発表する人が発表しやすいようにまとめることが求められます。
また、議論の流れが分かりやすくなるように構造化して書くことも必要です。
3.タイムキーパー
タイムキーパーは、全体の持ち時間から逆算して、議論の段階ごとの時間管理を行う役割を果たします。
どの段階にどれくらいの時間を要するのかを適切に見極め、議論が白熱したときも冷静にゴールに向かって皆を導くことが必要です。
しかし、単純にタイムキーパーを行うだけでは十分でなく、それと並行して貢献度の高い発言をすることが必要です。
4.発表者(プレゼンター)
発表者(プレゼンター)は、班でまとめた意見を最終的に発表する役割です。
考えが伝わりやすいように話すことができるのはもちろん、簡潔かつ論理的に話すことも求められます。
このようにグループディスカッションにはいくつかの役割がありますが、必ずしも時間を使って役割を決める必要はありません。
意見を出し合う中で自然と決まる、自然と任されることが多いので、「絶対にスタートでこの役割を奪い取る」という意識ではなく、自分の適性を考えつつ、チームに貢献するために今何をすべきかという視点を持つとチームとしての議論が深まります。
| 選考対策に強い就活サイト | ||
|---|---|---|
| エージェント名 | 評価 | ポイント |
>> OfferBox公式へ | ★5.0 | 【自分の強みがわからない方へ】 28項目の診断で自分の適性を知ることができる |
>> キャリアチケット就職スカウト公式へ | ★4.8 | 【選考対策が苦手な方へ】 5つの質問から自己PRやガクチカの作成も簡単に作成できる |
>> Lognavi公式へ | ★4.5 | 【性格テストで自分にあった企業を見つけられる】 5段階の相性診断で自己理解が深まる |
グループディスカッションで書記がおすすめな理由

上述したように、グループディスカッションでは議論にいくつかの段階があり、また多くの場合個人に役職を割り当てて進めます。
そのため、選考を突破しやすい役割を担い、それぞれの段階で活躍することができれば人事の方に自分をアピールすることができます。
実は、「書記」を率先して担当することで、選考を突破しやすくすることができるんです!
もちろん個人の適性は人によって違うため全員には当てはまらない可能性もありますが、グループディスカッションを突破できずに悩んでいる方は是非実践してみてください。
書記を担当することで選考を突破しやすくなる理由は、以下の2つです。
- 今までの議論を構造的に把握できるから
- 発言の内容を忘れにくいから
順に解説します。
理由1:今までの議論を構造的に把握できるから
書記を担当して議論の流れに沿ってまとめをすることで、流れの中で抜けている部分や論理の甘い部分に気付きやすくなります。
抜けている点や甘い点を補う発言をすることで、「論理的かつ網羅的に考えられている」という印象を持たせることが可能になります。
さらに、それらの点についてあまり発言できていない人や、その部分について発言した人に意見を求めることで、コミュニケーション能力をアピールすることができます。
このように議論全体が見えていることをアピールする手段として書記は非常に有効です。
理由2:発言の内容を忘れにくい

書記を担当することで、個々人の発言を逐一書き記していくため、メンバーの発言を忘れにくくなります。
それによって、人の話をよく聞けているという印象を与えることができます。
このような理由から、書記を担当することで人事担当者や面接官にチームで働く力をアピールすることができるのです。
ただし、人の話を聴けていることは、「〇〇さんの先ほどのアイデアですが……」と具体的に聞いていたアピールをしなければ意味がないため、その点に注意しましょう。
グループディスカッションで書記をやるときのコツ

書記は、単純に内容を書くだけでは不十分です。
書いた内容を頭を整理することで初めて議論を深める、もしくは前進させる発言ができるようになります。
書記に就いた場合は、自分の頭で構造化しようとする意識を持つようにしましょう。
議論を構造化するためには、ロジカルツリーと呼ばれる図をイメージすることをおすすめします。
ロジカルツリーとは、ある課題を解決するためには何をしたらいいのかという、課題と解決策が樹形図のように連なっている図のこと。
書記を担当して議論を見やすいようにまとめつつ、ロジカルツリーを頭の中でイメージすることで自然と今何をすべきかが見えやすくなります。
グループディスカッションのメンバーで『やりづらい人』への対処法3つ

ここまでは、書記を担当してグループディスカッションで能力をアピールするコツについて紹介しました。
そうは言っても、グループにチームでのワークを進める上でやりづらい人がいる場合、対処しなければ自分の能力を発揮することができずに終わってしまう可能性が高いです。
ここからは、以下のやりづらい人3パターンとそれぞれの対処法について紹介します。
対処法
- 自分の意見を曲げようとしない人
- 他人が話す時間を与えない人
- ほとんど喋らない人
順に解説します。
1.自分の意見を曲げようとしない人
チーム全体としての考えが自分と異なってきたとしても、自分の意見を通したいが故に意見を曲げようとしない人とチームメンバーになる可能性があります。
そのような人とチームになった場合、まずは表でメリットやデメリットを書き出すなどして、客観的な評価をもとに説得してみましょう。
ただ感情的に説得しても、当然納得してはもらえません。
あくまで「意見を通したいから」もしくは「急ぎたいから」ではなく、「客観的に優れているから」という観点で説明を試みましょう。
それでも納得してもらえない場合は、その意見を取り入れつつ全体の意向に沿うような案を考えましょう。
説得するのに比べて、「自分の意見が採用された」と感じて納得してもらえる可能性が高くなります。以下の2点のポイントを押さえましょう。
ポイント
- 客観的な評価をもとに説得する
- 一見相手に有利に見えるような説得を試みる
2.他人が話す時間を与えない人
グループディスカッションという限られた時間の中で人事の方に自分を売り込もうという意識が強すぎるあまり、自らがほとんどの時間話すことで主導権を握ろうとする人が存在します。
グループディスカッションはチーム全体で合意形成して施策に落とし込む過程をみているため、特定の人が進めすぎるのは当然評価されません。
そのような人とチームになった場合は、自分が積極的に他の人に意見を求めてみましょう。
そうすることで意図的に全体の意見を踏まえた合意形成をすることができると共に、人事の方に周りが見えているということをアピールできます。
また、人が喋るのを制してまで自分で進めようとする人に対しては、「大事な作業なんだけど任せていいかな」などと作業を任せることで他の人が入り込む余地をつくり出すのも良いでしょう。
ポイント
自分が率先して他の人の意見に耳を傾ける
喋ること以外の役割を与えて他の人が発言しやすい環境を作る
3.ほとんど喋らない人
グループディスカッションに参加すると、多くの場合少なくとも1人はあまり喋ることのできない人がいます。
議論に口を挟むタイミングが掴めない人や、発言の質を意識するあまり考え過ぎてしまう人など理由はさまざまです。
そのような人と一緒になったら、適当なところで「○○さんはどう思いますか?」と意見を求めてみましょう。
そうすることで、ほとんど話さない人に議論に入るきっかけを与えられるのと同時に、人事担当者に協調性があるという印象を与えることができます。
また、話すことが思いつかないために発言回数が少ないのではないかと感じたならば、「この部分の○○という意見についてはどう思う?」などと、聞くポイントを絞って簡単な質問をしてみましょう。
ポイント
聞くポイントを絞って、簡単に答えやすい質問を投げかけてみる
自己分析をやり込み、グループディスカッションに備えよう
グループディスカッションで高評価を得るには、自己分析を通して、「あなた自身」を深く理解しておくことが重要です。ただ、そんな時間がない方も多いはず。
自己分析で大事なのは、”企業が求める能力と自分の能力が合っているかどうか”を判断することです。
自分にどんな強み・能力があるかを素早く正確に把握できるのが、スカウト型就活サービスを提供しているOfferboxのAnalyze U+という機能です。
Analyze U+は、自己分析の精度が高いのはもちろん、その結果に興味をもった企業からスカウトが届きます。
実際にプロフィールを80%以上入力した学生のオファー受信率は、93.6%。5分で登録できるので、今すぐ登録して自分の強みを把握するようにしましょう!
\無料で自己分析/
選考対策におすすめの就活エージェント
ここではおすすめの就活エージェント5社を紹介します。
キャリアパーク
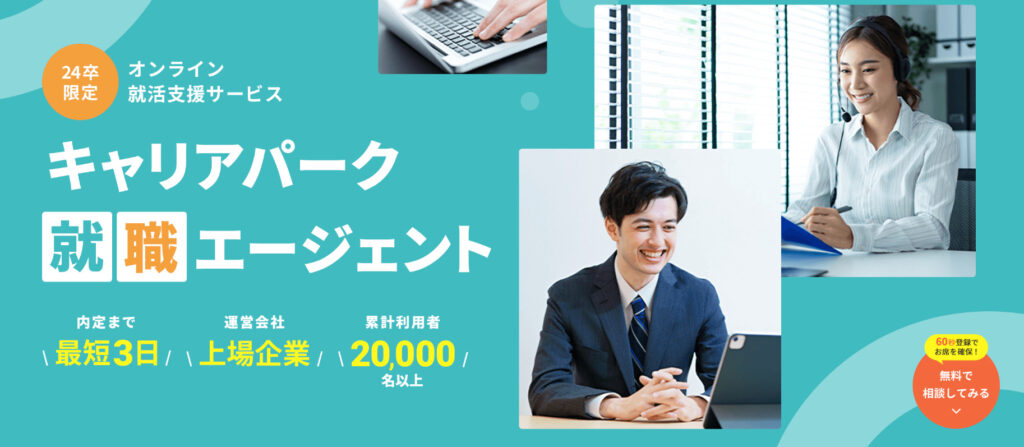
キャリアパークは特別の選考フローや選考回数が少ない求人を取り揃えているため、内定まで早くて1週間、最速3日で内定獲得も狙えます。
また、平均5回以上の面談や選考対策のセミナーなどあなたの就活をトータルでサポートしてくれます。
なかなか内定がもらえない方や今すぐ内定が欲しい方は、年間1,000名以上の面談を行うキャリアアドバイザーのサポートを借りて、就活を成功させましょう。
| サービス概要 | |
|---|---|
| サービス名 | キャリアパーク |
| 運営会社 | ポート株式会社 |
| 公開求人数 | 優良求人を直接ご紹介 |
| 対応地域 | 全国 |
| 公式サイト | https://careerpark.jp/ |
シュトキャリ
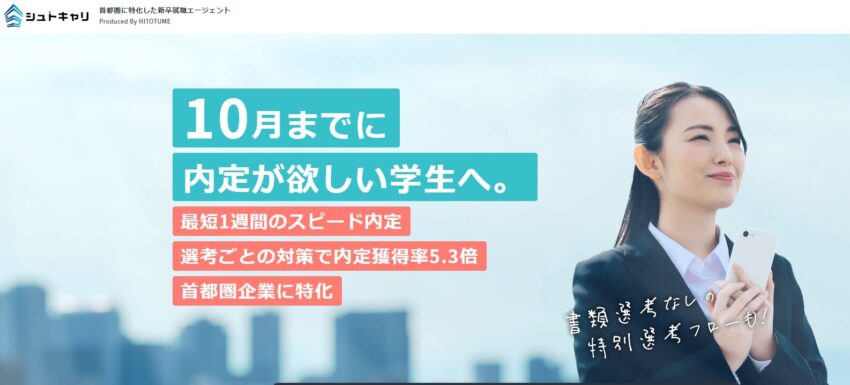
「シュトキャリ」は首都圏の企業に特化しており、企業ごとの理解度が高くミスマッチのない求人を紹介できるの強みの就職エージェントです。
シュトキャリは、書類選考なしの特別選考フローを保有しています。最短1週間のスピード内定も実現可能で、就活に時間をかけたくない方におすすめです。
オンライン面談が可能なため、地方在住でも利用できます。「首都圏での就職を希望している」「首都圏の企業は倍率が高くなかなか内定がもらえない」と悩んでいる方は無料登録してみましょう。
| シュトキャリの詳細情報 | |
|---|---|
| 運営会社 | ヒトツメ株式会社 |
| 公開求人数 | 優良求人を直接ご紹介 |
| 非公開求人数 | 非公開 |
| 公式サイト | https://hitotume.co.jp/shutocari/ |
ジール

「ジール」は、年間利用者数12,000人を超える新卒学生に特化した就活エージェントで、厳選された3,000社以上の企業から求人を提供し、就活のプロから1対1のサポートを受けることができます。
エントリーシートの書き方や面接など、選考に関わることはなんでもサポートしてもらえます。
また、最短2週間で内定を獲得することができるため、「内定が無くて焦っている…」学生におすすめのエージェントです。
| サービス概要 | |
|---|---|
| サービス名 | ジール就活エージェント |
| 運営会社 | 株式会社ジールコミュニケーションズ |
| 対応地域 | 東京、大阪、名古屋 |
| 公式サイト | https://zeal-shushoku-agent.com/ |
キャリアチケット

「キャリアチケット就職エージェント」は、単なる求人紹介には留まらず、入社後の未来を見据えた就職サポートに力を入れています。
やみくもにあらゆる企業を受ける就活ではなく、徹底したサポートを受けることで希望する企業への内定が目指せます。
「長いキャリアを見据えた就職活動」をサポートするため、専任の就活アドバイザーが一人ひとりの就職活動を支援し、自身が望むキャリアにとって重要なことをプロの目線でアドバイスしています。
有名企業に固執せず、「活躍できる企業」「必要なスキルを身につけられる企業」を基準に紹介してくれるため、自身の可能性を広げられるでしょう。
| サービス概要 | |
|---|---|
| サービス名 | キャリアチケット就職エージェント |
| 運営会社 | レバレジーズ株式会社 |
| 対応地域 | 東京、名古屋、大阪、京都など全国 |
| 公式サイト | https://careerticket.jp/ |
キャリアスタート
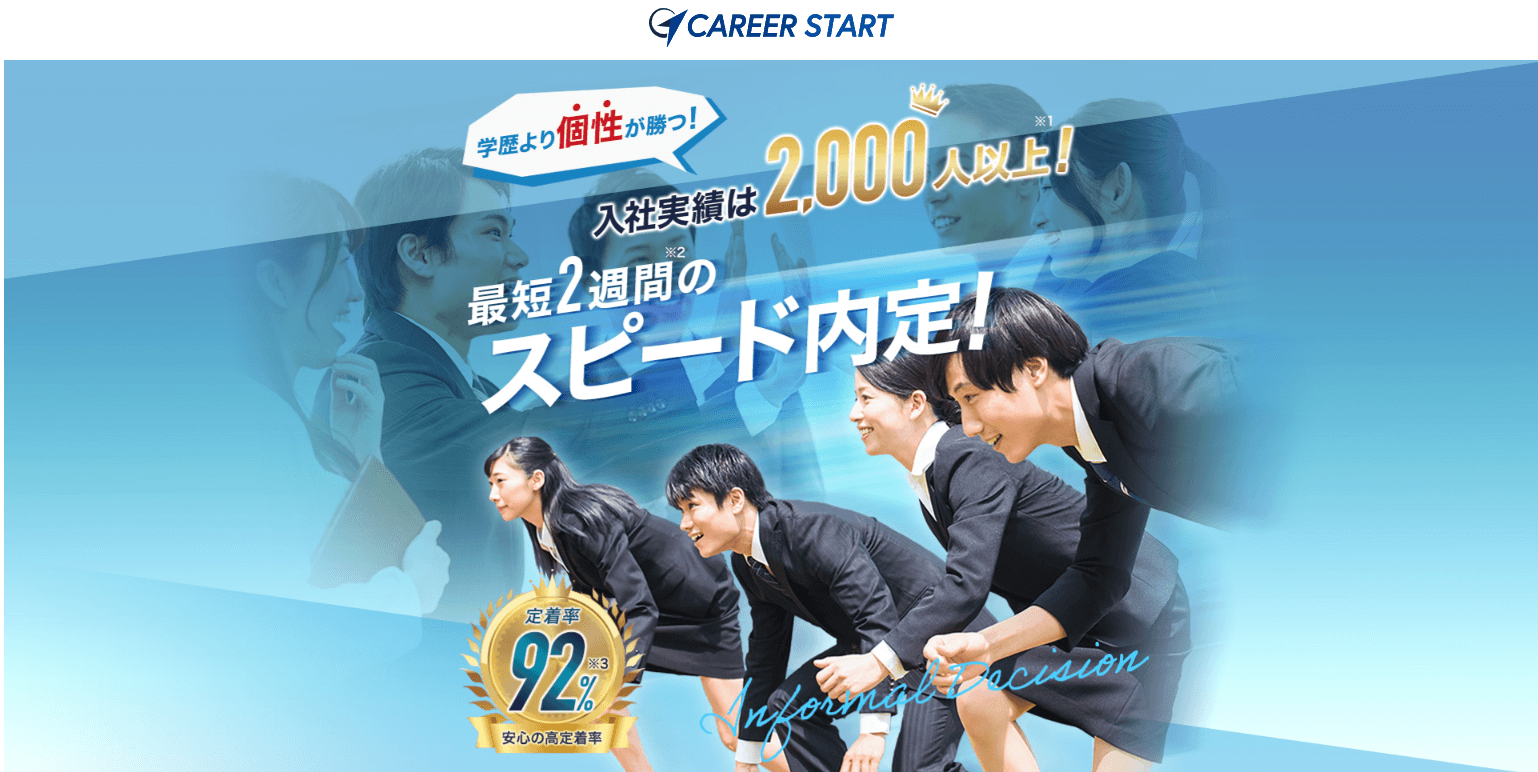
「キャリアスタート」は学歴より個性を重視した就活エージェントサービスで、就活支援実績は4,000名を超えています。
キャリアアドバイザーは、希望を踏まえた上で適性を見極めながら最適な求人を紹介してくれます。また、企業へのインタビューや調査を徹底しているため、入社後に後悔のない就職活動が可能です。
「自分にあった仕事ってなんだろう」「この会社に就職して本当に大丈夫だろうか」と心配や不安を抱えている方におすすめです。
| サービス概要 | |
|---|---|
| サービス名 | キャリアスタート |
| 運営会社 | キャリアスタート株式会社 |
| 公開求人数 | 優良求人を直接ご紹介 |
| 非公開求人数 | 非公開 |
| 対応地域 | 全国 |
| 公式サイト | https://careerstart.co.jp/ |
まとめ
この記事では、グループディスカッションを突破するためのコツについて紹介しました。
グループディスカッションでは書記をつとめて議論を構造化したり、他の人の発言を拾うようにすると上手くいきやすいということがわかりましたね。
また、時々現れる「やりづらい人」に対しては、タイプにあった対策をすると良いということも解説しました。
この記事で紹介したことを活かして、集団で上手く立ち振舞えるようになり、内定に近づきましょう!
グループディスカッションを突破したら、次のステップとして面接が課されることも多いです。
以下の記事で面接の際に意識したいマナーについて解説しているので、こちらも参考にしてみてください!

| 選考対策に強い就活サイト | ||
|---|---|---|
| エージェント名 | 評価 | ポイント |
>> OfferBox公式へ | ★5.0 | 【自分の強みがわからない方へ】 28項目の診断で自分の適性を知ることができる |
>> キャリアチケット就職スカウト公式へ | ★4.8 | 【選考対策が苦手な方へ】 5つの質問から自己PRやガクチカの作成も簡単に作成できる |
>> Lognavi公式へ | ★4.5 | 【性格テストで自分にあった企業を見つけられる】 5段階の相性診断で自己理解が深まる |